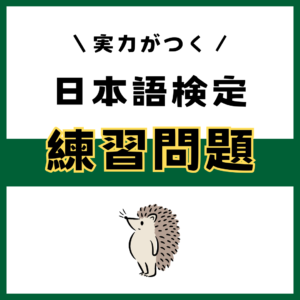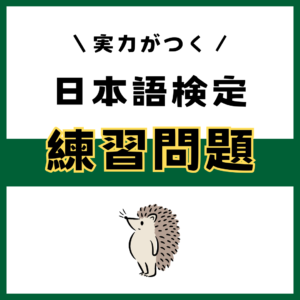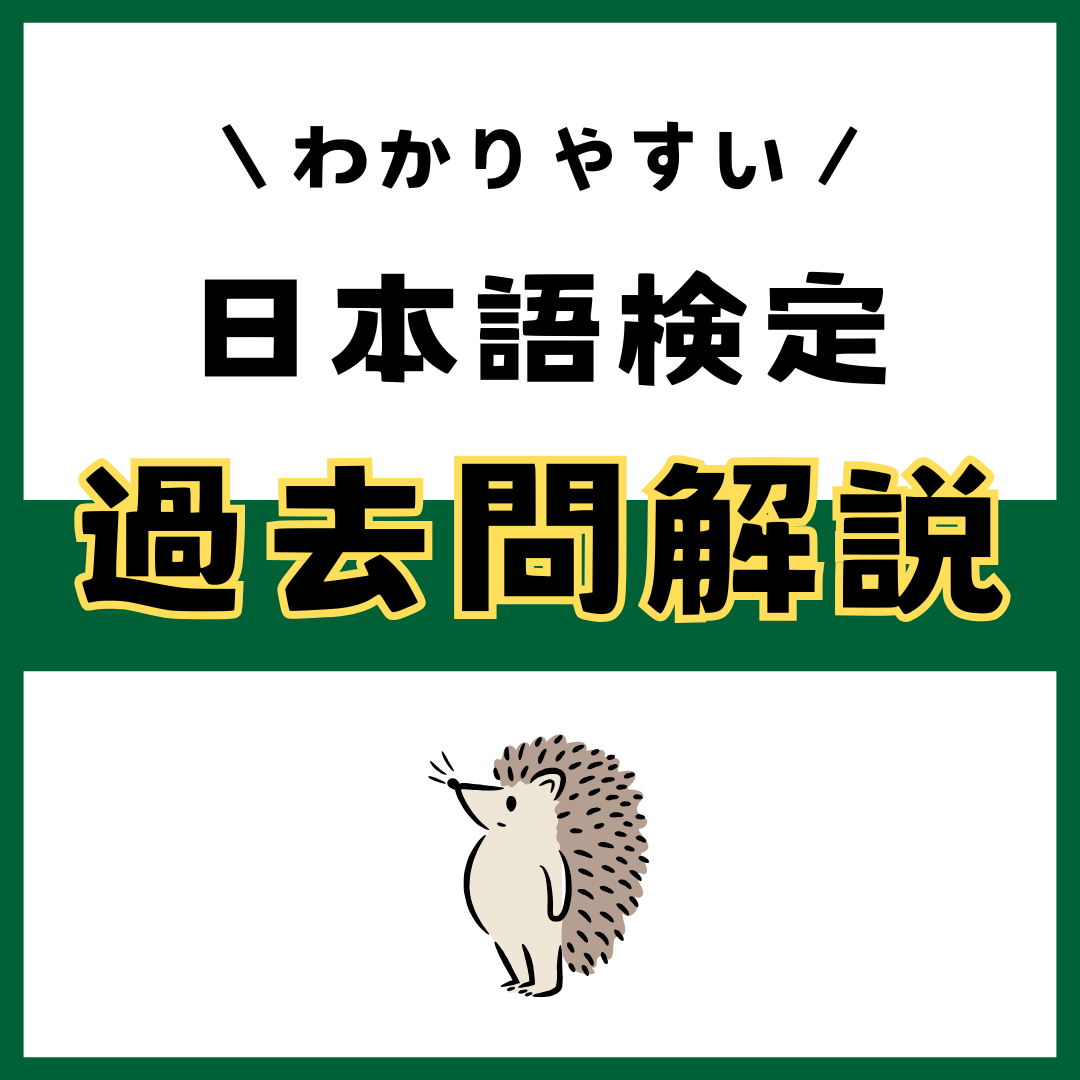はりねずみ隊長
はりねずみ隊長著作権の関係上、問題は掲載していません。
以下をご用意の上で、ご確認ください。
前の問題
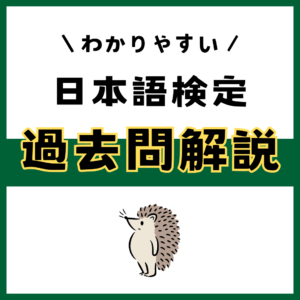
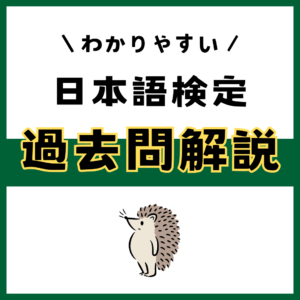
問16 総合問題
一


解説 随時
二 A


「先日27歳の誕生日を迎え…」から始まる第1段落の内容を見ていきましょう。
孤独に関する調査結果によると、孤独感が
- 常にある
- 時々ある
と答えた人の割合が
- 20代が最も高い
- 30代が2番目に高い
となっていたとのことです。
筆者の高田さんは、
(A)と思っていたが、実際は異なるようだ。
とある通り、意外な結果だと感じていたことがわかります。
その理由は、「20代・30代のような若い世代の人々は、SNSを介して常に他者と接しているため」と記載がありますね。
- 20代・30代のような若い世代の人々は、SNSを介して常に他者と接している
- だから、(A)と思っていたら、実際にはそうではなかった
という内容なので、(A)に入るのは、
3 孤独感とは無縁である
が適切です。
二 B


「先の調査によると…」から始まる第4段落の内容を見ていきましょう。
(B)が入る文のあとには、
思えば、私にも悩みを相談できる相手がいない。
という文が続きます。
- 調査結果と私の状態も同じだ
という内容になるので、(B)に入るのは、
2 悩みなど相談できる相手がいない
が適切です。
三


「図1は…」から始まる第2段落の内容を見ていきましょう。
言及されている図1では、SNSの利用頻度ごとにどれくらい孤独を感じるかの結果が記されています。
| SNSの利用頻度が… 週4~5回以上 | 孤独を感じることが決してないと答えた割合が… 32% |
| 週2~3回程度 | 24% |
| 週1回程度 | 20% |
| 2週間に1回程度 | 22% |
| 月に1回程度 | 20% |
| 月に1回未満 | 16% |
| 全くない | 22% |
- SNSを利用することが全くない
と答えた人の中で、
- 孤独を感じることが決してない
と答えた人の割合は、22%です。
これは、他と比べて、極端に高くも低くもない数値ですね。
この時点で、「明らかに…」が入った1・3を選択肢から除外することができます。
(イ)が入る文のあとには、
SNSを全く利用していない人々の中で、孤独を感じることが決してない人が22%であるということは、他者と接する機会の多さだけが孤独感の有無を決めるわけではないという可能性もあるのではないだろうか。
という内容が続きます。
筆者である高田さんは、
- SNSの利用頻度と孤独を感じることの間には関連がある
- SNSの利用頻度が高い人は、孤独を決して感じない人の割合が高い
- ということは、SNSを全く利用しないのであれば、孤独を決して感じない人の割合が低いはずだ!
- しかし、SNSを全く利用しない人でも、「孤独を感じることが決してない」の割合が22%であり、予想に反して(イ)結果だった
- そのため、他者と接する機会の多さだけが孤独感の有無を決めるわけではないという可能性もあるのではないか
と考えていますね。
(イ)には、
2 決して低くはない
が適切です。
四


表1では、
- 孤独をよく感じる人
- 孤独をあまり感じない人
がそれぞれ現在の孤独感に至る前にどのような経験をしたかが集計されています。
表1について述べている「では、人はどのようなときに…」から始まる第3段落を見てみましょう。
- 想定通り、他者とのつながりに関連する出来事から孤独を感じることが多い
- 他方で、一見他者とのつながりとは関係がなさそうなできごとも孤独感に結び付いている
- 孤独は、どんな出来事でも、それが引き金となって引き起こされ得る感情なのかもしれない
という内容が説明されていますね。
その出来事を経験したと答えた
- 孤独をよく感じる人
- 孤独をあまり感じない人
の割合が比較できるとわかりやすくなるので、1の形式が適切です。
2のように、
- 孤独をよく感じる人
- 孤独をあまり感じない人
それぞれで、経験したと答えた人の割合が高い出来事から順に並べると、孤独をよく感じる人は
- 一人暮らし
- 家族との死別
- 心身の重要なトラブル
- 転校・転職・退学・休学
- 人間関係による重大なトラブル
孤独をあまり感じない人は
- 一人暮らし
- 家族との死別
- 転居/転校・転職・退学・休学
- 心身の重要なトラブル/家族以外の親しい知人等との死別
- 家族との離別
となり、項目ごとの比較がしにくくなってしまいます。
3のように、
- 孤独をよく感じる人
- 孤独をあまり感じない人
の回答結果を合算すると、両者の割合が比較できなくなってしまいます。
4のように、
- 孤独をよく感じる人
- 孤独をあまり感じない人
それぞれで経験したと答えた人の割合が高い出来事を5つ選ぶと、両者で違う項目が並ぶことになり、項目ごとの比較がしにくくなってしまいます。
次の問題
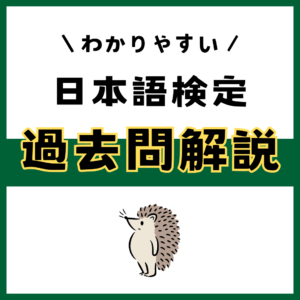
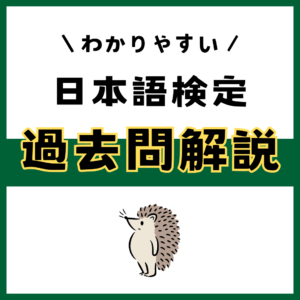
過去問解説の一覧
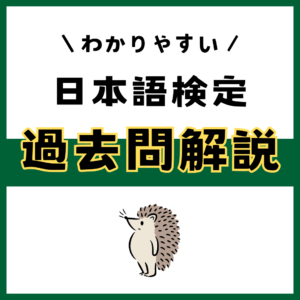
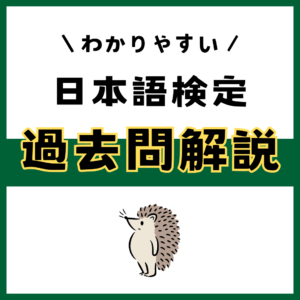
過去問で確認したいこと
特に、
- 敬語
- 文法
の2分野は、「解説を見れば、なんとなくわかるんだけど…」となりやすいのではないかと思います。
過去問を解いたときに、間違えた問題ごとに意識したいのは、
「そもそも知識がなくて解けなかった」
「知ってはいたが、問題になると解けなかった」
のどちらなのかを明確にすることです。
前者であれば、過去問を丁寧に解きながら、1つずつ知識の穴を埋めていきましょう。
- 語彙
- 言葉の意味
- 漢字
のような分野であれば、まとめて暗記していけるのですが、
- 敬語
- 文法
のような分野は、問題の文脈とセットで取り組むのがおススメです。
また、後者であれば、多くの練習問題で知識と問題のギャップをなくしていきましょう。
「わかる→できる」になることで、問題を解くスピードを上げていくことが大切です。
日本語検定は、1級から4級で、
- 語彙・言葉の意味・漢字などの聞かれる範囲が異なる
- 1問1問の難易度が異なる
という違いはあるものの、
- 敬語
- 文法
のような難易度が高い分野で必要な知識に大きな差があるわけではありません。
敬語であれば、
- 尊敬語
- 謙譲語Ⅰ
- 謙譲語Ⅱ
- 丁寧語
- 美化語
の5分類がそれぞれ「どのように定義されているか?」「どのような語が該当するか?」を整理しておきましょう。
その際に、単語を覚えていくのではなく、文章の中で登場人物を確認しながら見ていくのがおススメです。
文法であれば、
- 動詞
- 副詞
- 助詞
などの品詞ごとに、それぞれの語のもつ用法(使い方)を整理しておきましょう。
例えば、
買い物に行くので、8時に駅に集合してください。
には、3つの格助詞「に」がありますが、すべて用法が違います。
買い物に
の格助詞「に」は、「行く」という移動の目的を表しています。
また、
8時に
の格助詞「に」は、時を
駅に
の格助詞「に」は、「集合する」という移動の着点を表していますね。
まとまった参考書・問題集はないので、過去問で出てきた語の用法を1つずつノートなどにまとめていくのがおススメです。
この「日本語検定ナビ」では、分野ごとの練習問題を多数掲載しています。
- 過去問を解いていて、不安が残る分野
- もっと解くスピードを上げたい分野
があれば、ぜひご活用ください。