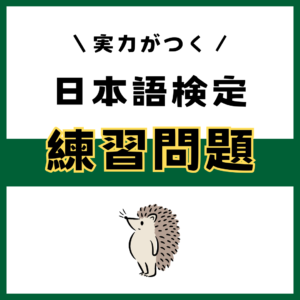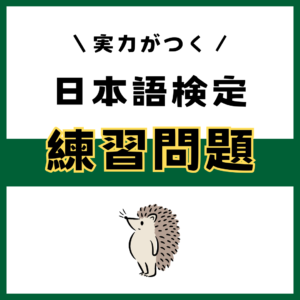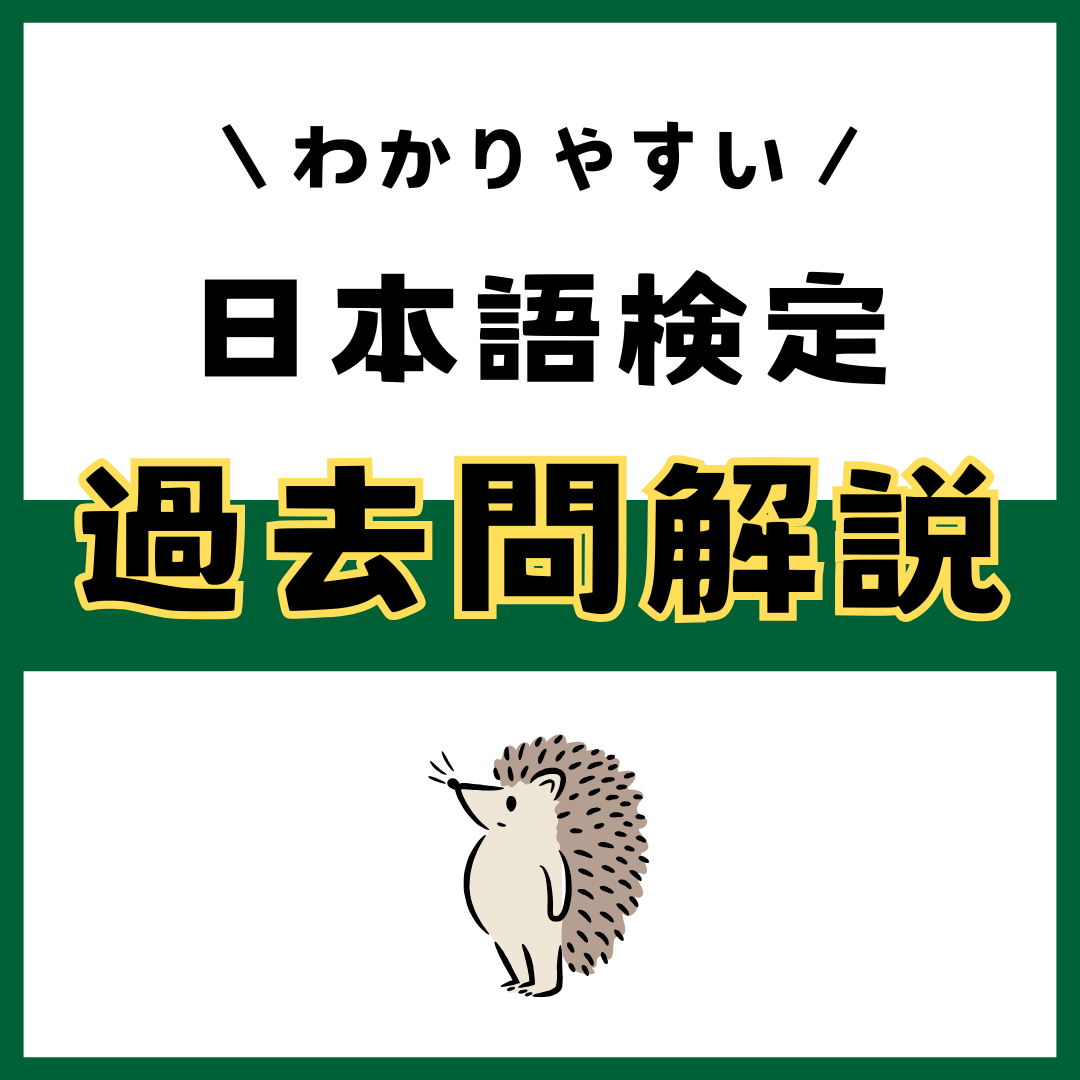はりねずみ隊長
はりねずみ隊長著作権の関係上、問題は掲載していません。
以下をご用意の上で、ご確認ください。
前の問題
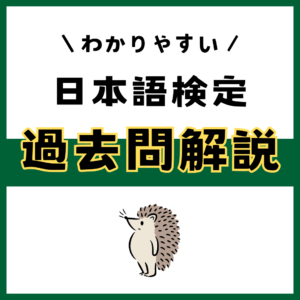
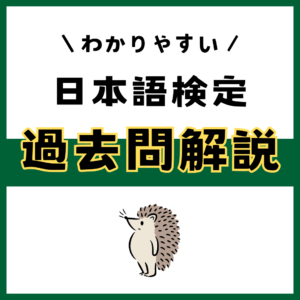
問3 敬語
ア


行ってちょうだい
は、
行ってください
のくだけた表現ですね。
1 いらっしゃってくれますか
では、
「行く」の尊敬語である「いらっしゃる」
恩恵を表す「くれる」
丁寧語の「ます」
が使われています。
尊敬語である「いらっしゃる」は問題ないのですが、恩恵表現に丁寧さがありません。
1は、間違いです。
2 行ってやってくれませんか
では、
恩恵を表す「くれる」
丁寧語の「ます」
が使われています。
「行ってやる」は、誰かに行かせることなので、意味が変わってしまいますね。
2は、間違いです。
3 いらっしゃってもらえますか
では、
「行く」の尊敬語である「いらっしゃる」
恩恵を表す「もらう」
丁寧語の「ます」
が使われています。
尊敬語である「いらっしゃる」は問題ないのですが、恩恵表現に丁寧さがありません。
3は、間違いです。
4 行ってくださいませんか
恩恵を表す「ください」
丁寧語の「ます」
が使われています。
丁寧な依頼表現として、適切ですね。
4は、正しいです。
尊敬語とは?
相手側又は第三者の行為・ものごと・状態などについて,その人物を立てて述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
イ


1 ~までうかがったらいいんですね
では、
「行く」の謙譲語Ⅰである「うかがう」
丁寧語の「です」
が使われています。
「時計屋」は立てるべき相手ではないため、謙譲語Ⅰは不適切です。
また、確認表現に丁寧さが足りないのも良くないですね。
1は、間違いです。
2 ~までいらっしゃればいいんですね
では、
「行く」の尊敬語である「いらっしゃる」
丁寧語の「です」
が使われています。
尊敬語の「いらっしゃる」は問題ないのですが、これも確認表現に丁寧さが足りません。
2は、間違いです。
3 時計屋様の前まで
では、「様」をつける必要がないにもかかわらず、「時計屋様」としてしまっています。
3は、間違いです。
4 ~まで参ればよろしいんですね。
「行く」の謙譲語Ⅱである「参る」
丁寧語の「です」
が使われています。
自分側の行為を聞き手に丁重に述べることができていますね。
4は、正しいです。
謙譲語Ⅰとは?
自分側から相手側又は第三者に向かう行為・ものごとなどについて,その向かう先の人物を立てて述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
尊敬語とは?
相手側又は第三者の行為・ものごと・状態などについて,その人物を立てて述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
謙譲語Ⅱとは?
自分側の行為・ものごとなどを,話や文章の相手に対して丁重に述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
ウ


1 止めていらっしゃっても
では、
「いる」の尊敬語である「いらっしゃる」
が使われています。
運転手の行為を立てて述べているので、適切な表現ですね。
1は、正しいです。
2 お止めされていても
では、
「止める」の謙譲語Ⅰである「お止めする」
尊敬の助動詞「れる」
が使われています。
尊敬の助動詞「れる」は問題ないのですが、向かうべき相手がいない行為なので、謙譲語Ⅰが適切ではありません。
2は、間違いです。
3 お止めになられていても
では、
「止める」の尊敬語である「お止めになる」
尊敬の助動詞「れる」
が使われています。
尊敬語を重ねており、二重敬語になっていますね。
3は、間違いです。
4 止めてくださっていても
では、
恩恵を表す「くださる」
が使われています。
運転手側の行為なので、恩恵表現は不要ですね。
4は、間違いです。
尊敬語とは?
相手側又は第三者の行為・ものごと・状態などについて,その人物を立てて述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
謙譲語Ⅰとは?
自分側から相手側又は第三者に向かう行為・ものごとなどについて,その向かう先の人物を立てて述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
エ


1 お戻りするまでお待ちしています
では、
「戻る」の謙譲語Ⅰである「お戻りする」
「待つ」の謙譲語Ⅰである「お待ちする」
「する」の謙譲語Ⅱである「いたす」
「いる」の謙譲語Ⅱである「おる」
丁寧語の「ます」
が使われています。
謙譲語Ⅰの「お戻りする」が運転手自身を立てているので、不適切ですね。
1は、間違いです。
2 お戻りまでお待ちになります
では、
「戻る」の尊敬語である「お戻り」
「待つ」の尊敬語である「お待ちになる」
丁寧語の「ます」
が使われています。
「お戻り」は問題ないのですが、「お待ちになる」だと運転手自身の行為を立ててしまっていますね。
2は、間違いです。
3 お戻りまで待たせていただきます
では、
「戻る」の尊敬語である「お戻り」
許可を受けて行う恩恵を表す「させていただく」
が使われています。
時計屋の前の道で待つことは、運転手が言い出していることではなく、最初から乗客の指示ですね。
尊敬語の「お戻り」は問題ないのですが、「させていただく」は適切ではありません。
3は、間違いです。
4 戻られるまでお待ちしております
尊敬の助動詞「れる」
「待つ」の謙譲語Ⅰである「お待ちする」
「いる」の謙譲語Ⅱである「おる」
丁寧語の「ます」
が使われています。
- 乗客が「戻る」
- 乗務員が乗客を「待つ」
なので、「れる」「お待ちする」は、いずれも乗客を立てることができていますね。
乗務員側の行為を乗客に丁重に述べる謙譲語Ⅱも問題ありません。
4は、正しいです。
謙譲語Ⅰとは?
自分側から相手側又は第三者に向かう行為・ものごとなどについて,その向かう先の人物を立てて述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
謙譲語Ⅱとは?
自分側の行為・ものごとなどを,話や文章の相手に対して丁重に述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
尊敬語とは?
相手側又は第三者の行為・ものごと・状態などについて,その人物を立てて述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
オ


1 ご面倒をかけられますが
では、
「面倒」の謙譲語Ⅰである「ご面倒」
受身の助動詞「れる」
丁寧語の「ます」
が使われています。
「面倒をかける」のは、乗客→乗務員なので、意味が逆になっていますね。
1は、間違いです。
2 面倒をかけなさいますが
では、
「なさる」という尊敬語
丁寧語の「ます」
が使われています。
乗客自身の行為である「面倒をかける」に尊敬語が使われているのが適切ではありません。
2は、間違いです。
3 ご面倒をおかけしますが
では、
「面倒」の謙譲語Ⅰである「ご面倒」
「かける」の謙譲語Ⅰである「おかけする」
丁寧語の「ます」
が使われています。
「面倒をかける」のは乗客から乗務員に向かう行為なので、謙譲語Ⅱは適切ですね。
3は、正しいです。
4 ご面倒になりますが
では、
「面倒」の謙譲語Ⅰである「ご面倒」
丁寧語の「ます」
が使われています。
あくまで事実を述べているだけであり、聞き手である乗務員を立てることができていません。
4は、間違いです。
尊敬語とは?
相手側又は第三者の行為・ものごと・状態などについて,その人物を立てて述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
謙譲語Ⅰとは?
自分側から相手側又は第三者に向かう行為・ものごとなどについて,その向かう先の人物を立てて述べるもの。
敬語の指針
平成19年度2月2日
文化審議会答申
次の問題
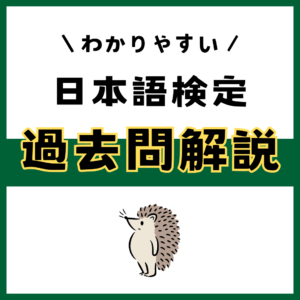
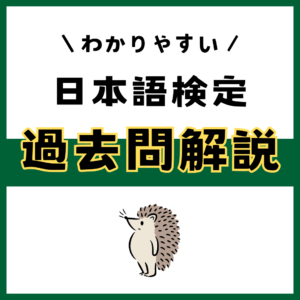
過去問解説の一覧
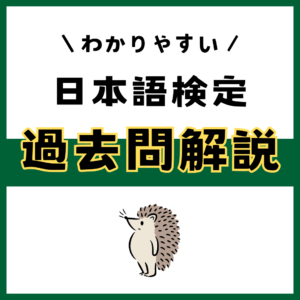
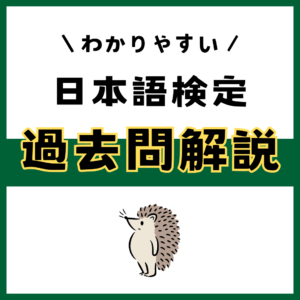
過去問で確認したいこと
特に、
- 敬語
- 文法
の2分野は、「解説を見れば、なんとなくわかるんだけど…」となりやすいのではないかと思います。
過去問を解いたときに、間違えた問題ごとに意識したいのは、
「そもそも知識がなくて解けなかった」
「知ってはいたが、問題になると解けなかった」
のどちらなのかを明確にすることです。
前者であれば、過去問を丁寧に解きながら、1つずつ知識の穴を埋めていきましょう。
- 語彙
- 言葉の意味
- 漢字
のような分野であれば、まとめて暗記していけるのですが、
- 敬語
- 文法
のような分野は、問題の文脈とセットで取り組むのがおススメです。
また、後者であれば、多くの練習問題で知識と問題のギャップをなくしていきましょう。
「わかる→できる」になることで、問題を解くスピードを上げていくことが大切です。
日本語検定は、1級から4級で、
- 語彙・言葉の意味・漢字などの聞かれる範囲が異なる
- 1問1問の難易度が異なる
という違いはあるものの、
- 敬語
- 文法
のような難易度が高い分野で必要な知識に大きな差があるわけではありません。
敬語であれば、
- 尊敬語
- 謙譲語Ⅰ
- 謙譲語Ⅱ
- 丁寧語
- 美化語
の5分類がそれぞれ「どのように定義されているか?」「どのような語が該当するか?」を整理しておきましょう。
その際に、単語を覚えていくのではなく、文章の中で登場人物を確認しながら見ていくのがおススメです。
文法であれば、
- 動詞
- 副詞
- 助詞
などの品詞ごとに、それぞれの語のもつ用法(使い方)を整理しておきましょう。
例えば、
買い物に行くので、8時に駅に集合してください。
には、3つの格助詞「に」がありますが、すべて用法が違います。
買い物に
の格助詞「に」は、「行く」という移動の目的を表しています。
また、
8時に
の格助詞「に」は、時を
駅に
の格助詞「に」は、「集合する」という移動の着点を表していますね。
まとまった参考書・問題集はないので、過去問で出てきた語の用法を1つずつノートなどにまとめていくのがおススメです。
この「日本語検定ナビ」では、分野ごとの練習問題を多数掲載しています。
- 過去問を解いていて、不安が残る分野
- もっと解くスピードを上げたい分野
があれば、ぜひご活用ください。